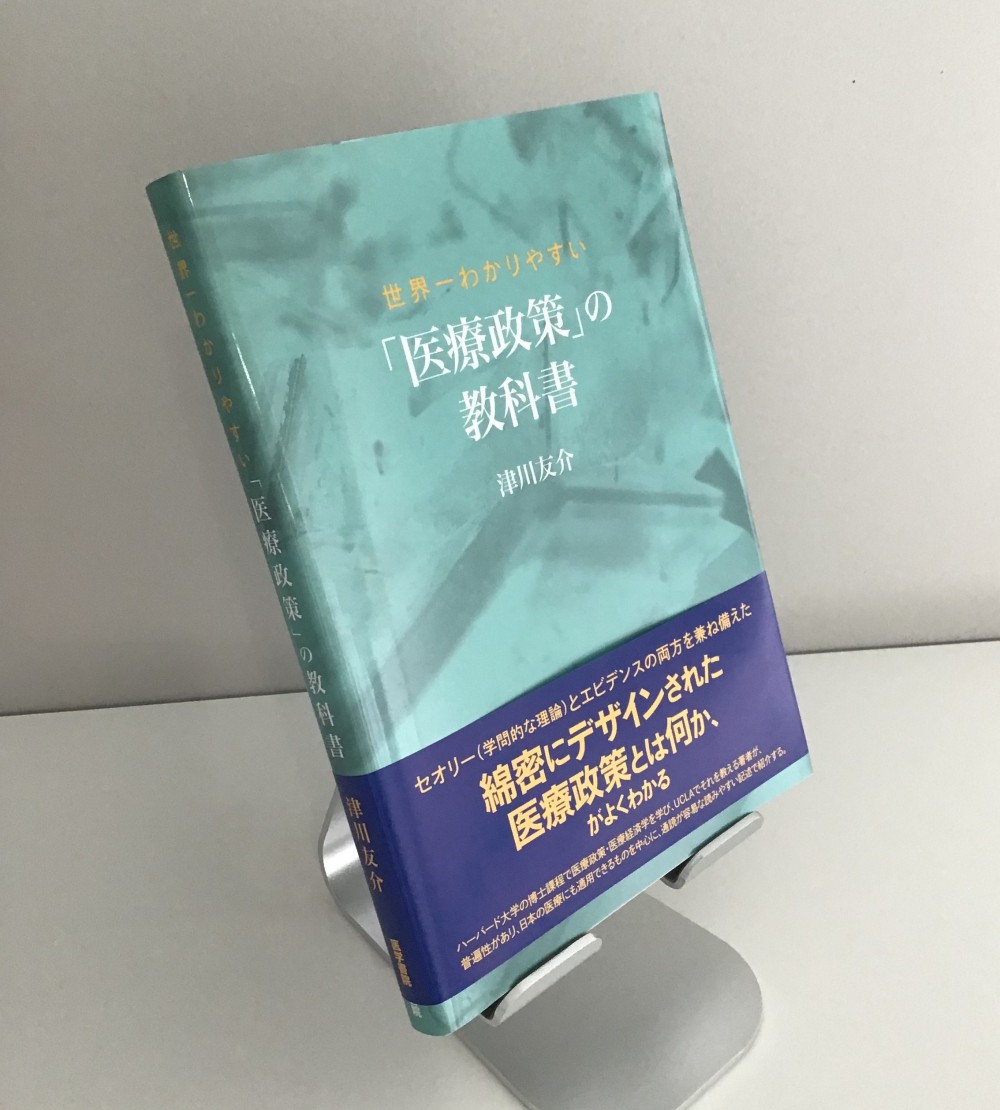
この度、『世界一わかりやすい「医療政策」の教科書』という名前の本を出版させて頂くことになりました。
医療政策を理解するのに必要な知識を系統立てて網羅し、そしてできるだけ前知識ゼロであっても理解できるようにわかりやすく説明した入門書です。
※こちらのリンクから予約して頂けます(6月1日発売予定)。
日本はかつてない少子高齢化社会を迎えており、それに加えて新型コロナウイルス感染による経済への悪影響というダブルパンチに対して、力を合わせて乗り越えようとがんばっています。
その中で、国民が安心して質の高い医療を受け、医療費増大による税や保険料の過度な負担を避けるためには、セオリー(理論)とエビデンス(科学的根拠)の両方を兼ね備えた「綿密に設計された医療政策」が必要不可欠になってきます。
欧米諸国では、大学、研究機関、シンクタンクなどで得られた知見が政策に生かされ、エビデンスに基づいた医療政策が立案され、それが実施されるようになってきています。
その一方で、日本では政策研究はあまり活発ではなく、その結果として、エビデンスに基づいた医療政策は期待されているほどには実現していません。
本書では、私がアメリカのハーバード大学で学び、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で教えている医療政策学に関するセオリーとエビデンスのうち、普遍性があり、日本にも適用できるものを中心にご紹介しています。
医療政策学とは単一の分野ではなく、複数の領域のセオリーとエビデンスを必要とする分野横断的な学問です。これらの領域に関して医療政策を理解するうえで必要な知識をカバーしました(詳しくはこの記事の最後の章立てをご覧ください)。

エビデンスに基づく政策立案(EBPM)
政策が目的とする成果を達成するためには、エビデンスに基づいた政策立案(Evidence-based policy making;EBPM)が必要不可欠です。
臨床医学が病態生理とエビデンスを組み合わせるエビデンスに基づいた医療(Evidence-based medicine;EBM)を通じて患者の健康を改善することを目指すように、医療政策学ではセオリー(主に医療経済学の理論)とエビデンスを組み合わせたEBPMを通じて、医療の質の向上や、医療費の適正化を実現します。

昔はデータが少なく医療政策学のエビデンスも乏しかったため、官僚や政治家などの実務家の経験を基に政策立案するのが現実的であったのでしょう。
しかし、現在ではデータもエビデンスも十分に存在するため、EBPMを軸に政策立案することが世界標準となりつつあります。
医療政策とPDCAサイクル
立案段階で完璧な政策というのはまれであるため、あらゆる政策は科学的な評価を受け、その結果をもとに微調整を加え続ける必要があります。つまり、ビジネスだけでなく、政策に関してもPDCAサイクルを回すことが重要なのです。
PDCAサイクルとはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の4段階を繰り返すことで業務を改善していく手法のことです。政策であればPは政策立案(政策の設計)、Cは政策評価となります。

しかし、政策立案した人と評価する人が同じであったら公正・中立な評価をすることは困難です。経済的なものに限らず様々な利益相反があることも多く、誰でも自分の関連する政策を客観的に批判的吟味するのは難しいためです。
そのため、欧米諸国では大学、研究所、シンクタンクなどの独立性・中立性が担保された研究機関(第三者機関)が主に政策評価の役割を担います。
つまり政策立案者(政治家、官僚)と政策研究者(アカデミア)の間で、健全なチェック・アンド・バランスの関係が成り立っているのです。
わかりやすい医療政策の入門書
本書には私がハーバード大学の医療政策学の博士課程で学んだこと、およびその後研究者としてハーバード大学やUCLAで得た知識のすべてを詰め込んでいます。
日本の現在の医療制度に関する細かい説明や、難しい数式はできるだけし、時代が変わっても永く使うことのできる普遍的な知識を中心に紹介しました。
この本を書くにあたって、多くの方にご支援頂きました。推薦文を、黒川清先生(日本医療政策機構代表理事)と横倉義武先生(日本医師会会長)に書いて頂きました。この場をお借りして御礼申し上げます。
私の師である、アメリカを代表する医療経済学者の一人である、ハーバード大学のジョセフ・ニューハウス教授も推薦のことばを寄せてくれました。

また、下記のような第一線で活躍している学者・実務家の方に原稿を読んで頂き、貴重なフィードバックを頂きました。ありがとうございます。
多くの方の協力を得て完成した本書ではありますが、本文中の誤りの一切は筆者の責によるものであることをお断りしておきます。
| 医療政策学 | 二木立先生(日本福祉大学)
池上直己先生(聖路加国際大学) |
| 医療経済学 | 西村周三先生(医療経済研究機構)
飯塚敏晃先生(東京大学) 後藤励先生(慶應義塾大学) 加藤弘陸先生(UCLA/慶應義塾大学) |
| 統計学・計量経済学(主に因果推論) | 伊藤公一朗先生(シカゴ大学)
星野崇宏先生(慶應義塾大学) 林邦好先生(聖路加国際大学) 井上浩輔先生(UCLA公衆衛生大学院) 芝孝一郎先生(ハーバード公衆衛生大学院) |
| 医療の質 | 東尚弘先生(国立がん研究センター)
五反田紘志先生(シーダース・サイナイ病院) |
| 医療社会学 | 近藤尚己先生(東京大学) |
| 費用対効果分析 | 五十嵐中先生(横浜市立大学) |
| 政策立案者(実務家) | 佐藤豪竜氏(厚生労働省)
松本晴樹先生(厚生労働省) |
政治家、官僚、医療関係者、医療業界やヘルスケア産業で働く人たち、医療政策を学びたい人たちだけでなく、医療に関心のある一般の方にもぜひ読んで頂きたい一冊です。医学部や公衆衛生大学院の教科書(入門書)としても最適だと思います。
この本を読んで頂くことで、医療がどのように機能しており、医療費が何によって決まるのか理解が深まります。これらは、社会保障費の議論をするために必須の知識です。
本書の内容をきちんと理解することができれば、ハーバード大学やUCLAの修士・博士課程に留学しなくても同水準の理解度に達することができるように工夫しました。
この本を通じて、日本の政策立案者・医療関係者・国民が、医療政策の本質に関してより深く理解し、その知識を道具として使いこなすことで「綿密に設計された医療政策」が日本でも実現し、日本が医療の質を保ちながら「持続可能な医療」の実現に成功することを切に願っています
『世界一わかりやすい「医療政策」の教科書』(医学書院)予約サイト
章立て
- 医療経済学
- 医療経済学の4つの起源
- ミクロ経済学の基本
- なぜ医療に市場原理が通用しないのか?
- モラルハザード
- 逆選択とリスク選択
- 医療サービスに市場原理が通用しない理由
- 医療費は水準よりも増加率が重要である
- 国の医療費増加の一番の原因は医療技術の進歩
- 医療保険のしくみ
- 医療保険を用いた世界初のランダム化比較試験「ランド医療保険実験」
- 無保険者に対する医療保険の影響を評価したランダム化比較試験「オレゴン医療保険実験」
- 医療サービスの価値によって自己負担割合が変わる医療保険「価値に基づく医療保険(VBID)」
- 医師誘発需要
- プリンシパル・エージェント・モデル
- 医療財源と、医療機関への支払制度
- 製薬産業
- 医師不足問題の考えかた
- 統計学
- 医療政策と統計学
- まずは研究の目的をはっきりさせよう
- 因果推論の3つの学派
- 実験と疑似実験
- 回帰分析
- より高度な回帰分析
- 政治学
- 医療政策と政治学
- キングドンのアジェンダ設定と政策の窓
- 経路依存性
- 争点と注目度の周期
- 中位投票者定理
- 決断科学(費用対効果分析)
- 医療政策と決断科学
- 費用対効果分析の基本的な考えかた
- 費用対効果分析の注意点
- オレゴン州の「優先順位リスト」から学べること
- 予防医療だからといって医療費抑制につながるとは限らない
- 医療経営学(医療の質)
- 医療の質と医療費は「車の両輪」
- QIを用いて医療の質を測り、改善を目指す
- 医療におけるP4Pのエビデンスは弱い
- 医療倫理学
- 医療政策と医療倫理学
- ロールズの正議論
- 健康の格差はどうして問題なのか?
- 健康の自己責任論
- 限りある資源をどのように分配したらよいのか?
- 医師の頭脳流出
- 医療社会学
- 社会の格差は、健康に悪影響を与える
- 「格差」と「貧困」のどちらが健康に悪いのか?
- オバマケアからトランプケアへ―アメリカの医療制度の現状
- オバマケアとはどんな政策だったのか?
- オバマケアの制度設計
- オバマケアへの評価
- オバマケアからトランプケアへ
